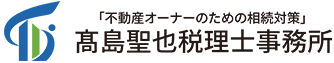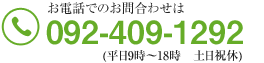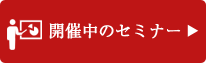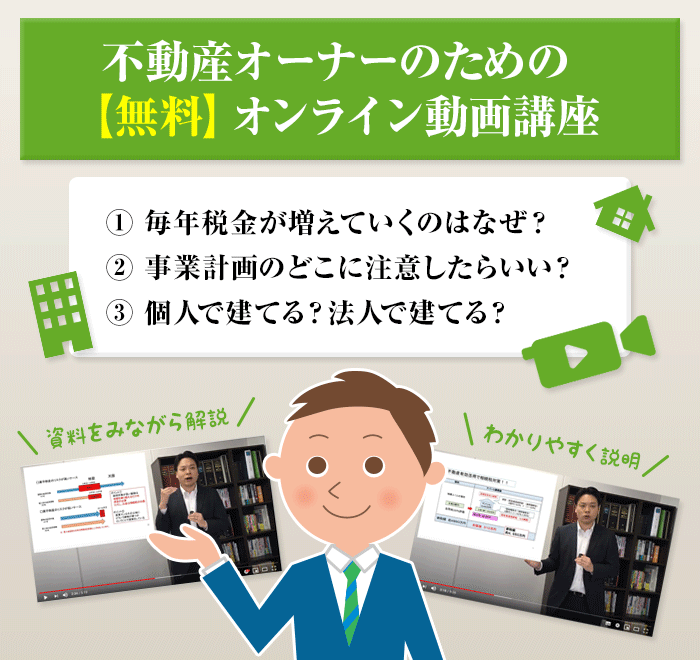現在、インフレの影響でさまざまな商品の価格が上昇しています。
私自身もスーパーで買い物をする際、「以前はこの値段だったのに」と驚き、購入を控えることがあります。
しかし、生活のためには必要なものを買わざるを得ません。
こうした状況の中で対応策を考えると、収入を増やすか、支出を抑えるかのいずれかが求められます。
こうした状況の中で対応策を考えると、収入を増やすか、支出を抑えるかのいずれかが求められます。
これは私の税理士事務所の経営においても同様ですし、賃貸経営においても同じことが言えます。
現在、賃貸事業を企画しているお客様が建築費や維持管理費の見積もりを取ると、
現在、賃貸事業を企画しているお客様が建築費や維持管理費の見積もりを取ると、
やはりコストの積み重ねによる価格上昇が見られます。
単純に家賃を上げるという選択肢もありますが、それが適切かどうかは物件の状況によります。
インフレ時の賃貸経営における考え方
たとえば、築25年以上の物件で駅から遠い立地の場合、共益費や清掃費、
エレベーターの修繕費が上がったからといって、単純に共益費を値上げするのは適切でしょうか。
会計上は収支を合わせるための合理的な方法に思えますが、入居者の視点ではどうでしょうか。
会計上は収支を合わせるための合理的な方法に思えますが、入居者の視点ではどうでしょうか。
他の物件と比較した際に「この物件の共益費が高い」と判断されれば、入居を躊躇される可能性があります。
そのため、
• 共益費の値上げが適切か
• 家賃を上げるべきか
• それ以外の方法で収支を調整できないか
など、多角的に検討する必要があります。
そのため、
• 共益費の値上げが適切か
• 家賃を上げるべきか
• それ以外の方法で収支を調整できないか
など、多角的に検討する必要があります。
数字を基にした戦略が重要
インフレの影響を把握するためには、まず会計上の数字を正確に捉えることが大切です。
そのうえで、
• 値上げで対応するのか
• 経費削減で対応するのか
• その他の方法を模索するのか
といった選択肢をシミュレーションし、仮説と検証を繰り返しながら適切な対応策を導き出すことが求められます。
私の税理士事務所でも、お客様に料金改定をお願いする場面があります。
• 値上げで対応するのか
• 経費削減で対応するのか
• その他の方法を模索するのか
といった選択肢をシミュレーションし、仮説と検証を繰り返しながら適切な対応策を導き出すことが求められます。
私の税理士事務所でも、お客様に料金改定をお願いする場面があります。
その際には、単に値上げをお願いするだけでなく、どのように売上を増やすべきかについても
助言を行うことが重要だと考えています。
価格競争から価値創造へ
今後、日本は人手不足が続くことが予想されます。
そのため、単に「どこが安いか」を基準に業者を選ぶだけでは対応が難しくなります。
今までは多少の値引きをしてでも仕事を取っていた企業も、
今後は「値引きをするくらいなら受注しない」という方向へシフトする可能性があります。
これからの時代は、
「どのように価値を生み出すのか」
これからの時代は、
「どのように価値を生み出すのか」
「その価値とは何か」
を経営の視点で捉え、数字を分析しながら戦略を立てることが重要になります。
価値の創造は、最終的に付加価値として粗利益に反映されます。
価値の創造は、最終的に付加価値として粗利益に反映されます。
単純にお金をかければ良いわけではなく、コストを抑えながらも入居者が「価値がある」と感じる工夫が求められます。
実際の事例:ターゲットを明確にすることの重要性
先日、ご紹介いただいたリフォーム会社や修繕会社の社長のお話では、
万人受けする提案よりも、ターゲットを絞ることが重要とのことでした。
例えば、住居だけを提案していたケースでも、
• 住居+店舗併用型にする
• 住居+事務所併用型にする
といった形にすることで、住宅費ではなく事業費として経費計上できるメリットを提供できます。
例えば、住居だけを提案していたケースでも、
• 住居+店舗併用型にする
• 住居+事務所併用型にする
といった形にすることで、住宅費ではなく事業費として経費計上できるメリットを提供できます。
これは入居者にとって新たな付加価値となります。
また、土地の面積が限られていて有効活用が難しい場合でも、
• カフェなどの店舗として活用する提案
また、土地の面積が限られていて有効活用が難しい場合でも、
• カフェなどの店舗として活用する提案
を行うことで、新たなビジネスモデルを生み出すことができます。
例えば、
カフェを開業するターゲット層(若年層や起業希望者)に向けた内装デザインを工夫することで、
同じ建築コストでも付加価値の高い物件として差別化することが可能になります。
もちろん、事業系の活用にはリスクも伴いますが、付加価値の創出方法はさまざまです。
もちろん、事業系の活用にはリスクも伴いますが、付加価値の創出方法はさまざまです。
賃貸事業においては、こうした価値の捉え方がますます重要になってきています。
まとめ:数字を把握し、戦略的に価値を生み出す
賃貸経営においては、
• 会計数字を正確に把握し
• 市場調査を行い
• 仮説検証を繰り返しながら戦略を立てる
ことが、今後ますます求められます。
私も引き続き、皆様に役立つ情報をお伝えしながら、
• 会計数字を正確に把握し
• 市場調査を行い
• 仮説検証を繰り返しながら戦略を立てる
ことが、今後ますます求められます。
私も引き続き、皆様に役立つ情報をお伝えしながら、
価値創造の視点での賃貸経営をサポートしていきたいと思います。
令和7年2月12日 税理士 髙島聖也